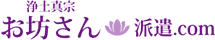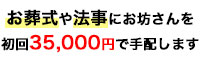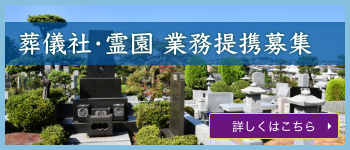永代供養のお墓は従来のお墓とは多くの部分で違いがあります。
しかし、具体的にどんな違いがあるのかよく理解していないという方もいらっしゃるでしょう。
例えば、永代供養と従来のお墓では期間の部分で大きな違いがあります。
今回は、そんな期間の違いについて解説します。
⑴ 永代供養の期間はいつまで?
永代供養は「永代」とついていることから、ずっと同じように供養し続けてもらえるものと考える方もいらっしゃるでしょう。
こうした考えは、半分合っていますが、半分間違っていると言えます。
永代供養では、遺骨の管理や供養を個別に行ってもらえますが、これには期間が定められています。
この期間のことを「安置期間」と言います。
安置期間を過ぎると、個別に管理・供養されていた遺骨は他の方の遺骨と合祀されます。
遺骨が供養されなくなるわけではなく、合祀される形になるだけであるため、「供養してもらえなくなるのではないか」、「きちんと管理してもらえなくなるのではないか」といった心配は不要です。
こうした意味で、「永代供養はずっと同じように供養してもらえる」という考えは「半分正しくて半分間違いである」と言えるのです。
なお、安置期間は施設や契約内容によって様々ですが、多くの場合、17回忌や33回忌、50回忌といった仏教的な法要年数を区切りとしている施設が多いです。
⑵ 従来のお墓の場合の期間は?
従来のお墓の場合は、「安置期間」のような期間は特に定められていません。
ただし、定期的に管理料を支払う必要があります。
管理料の支払いが行われなくなる、すなわち、お墓が放置されると、お墓が荒れ果ててしまったり、場合によっては撤去されたりしてしまいます。
お墓の撤去に関する規則は、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条」にて定められています。
管理者がお墓を撤去するには、立て札か官報にて「所有者は1年以内に申し出るように」と呼びかける必要があります。
こうした呼びかけがあるため、「知らないうちに撤去されてしまった」となることは基本的にはありません。
ただし、所有者が1年以上名乗り出ない場合には、お墓の撤去が行えるようになります。
お墓を撤去されるだけではなく、管理費を納めていなかった場合は未納分の管理費を請求される可能性もあります。
お墓の放置は多方面に迷惑がかかるだけでなく、費用を請求されたりする可能性もあるのです。
❖ まとめ
今回は、永代供養と従来のお墓の期間について解説しました。
永代供養には「安置期間」が定められており、その期間を過ぎると合祀されますが、管理や供養は引き続ききちんと行ってもらえます。
供養されなくなることはないため、安心して永代供養を任せられますね。
弊社【 浄土真宗 お坊さん派遣.com 】では、納骨堂 を京都市東山区に所有いたしており、
【永代供養】のご対応も万全です!( 宗派不問 )
近年では、生前中に【永代供養】のご予約をされる方が増えてまいりました。
❶ 交通の便が大変良い場所
❷ 無料駐車場完備
❸ 車椅子での参拝可
❹ 冷暖房完備
❺ お食事処も併設
❻ 法要ホール完備で貸切法要も可能
等々、ご親族そろってのご参拝に大変好評をいただいております!
『 納骨出来ないまま、遺骨が自宅にある 』
『 骨壺を夫婦・兄弟・姉妹・親子 横並びにしたい 』
『 遠方(故郷)の墓から住居の近くに遺骨を移したい 』
『 お墓の継承者がいない。墓じまいを検討中 』
『 お墓のことで将来子供や孫に心配をかけたくない 』
といった方におすすめです!!
費用は納骨の年数によって様々ですが、
関西地区 最安値 です!
※通常、【永代供養】=『合祀』(最初から他人の遺骨と一緒に納骨)が大半ですが、
弊社では依頼者様からの強いご要望にお応えし、
『合祀』ではなく、『個別安置』に特化 致しております。
いくつものプランがありますので、ご予算に合ったものをご選択可能です。
※ 事前のご見学も随時承っております。
関西地区で永代供養をする場所をお探しの方は、
どうぞお気軽に、弊社【 浄土真宗 お坊さん派遣.com 】までお電話(0120-44-4649)下さい。