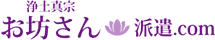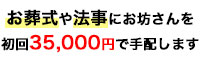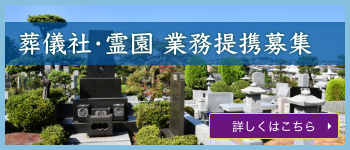法事の数え方や種類、意味など、法事に関することは複雑で、いざという時に何をすれば良いか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
特に、故人が亡くなってから初めての法事となると、何を準備すれば良いのか、どのような服装で参列すれば良いのか、お布施はいくら包めば良いのかなど、わからないことだらけです。
今回は、法事の基礎知識をわかりやすく解説することで、初めて法事を行う方でも安心して準備を進められるようにサポートします。
法事の数え方と種類
法事とは、故人を偲び、その冥福を祈るための儀式です。
仏教では、故人が亡くなってから一定の期間ごとに法要を行い、故人の霊を供養するとされています。
法事は、故人が亡くなってから1年目の命日に行う「一周忌」を皮切りに、3回忌、7回忌、13回忌、17回忌、23回忌、25回忌と、様々な節目で行われます。
1: 法事の数え方
法事の数え方は、満年齢ではなく、数え年で行います。
つまり、故人が亡くなってから1年が経過した時点で「一周忌」、2年が経過した時点で「三回忌」というように、亡くなった年から1年加えた年数が回忌の数となります。
2: 法事の種類
法事の種類は、回忌の数によって異なります。
主な法事の種類とその意味は以下の通りです。
・ 一周忌:故人が亡くなってから1年目の命日に行う法要。
・ 三回忌:故人が亡くなってから2年目の命日に行う法要。
・ 七回忌:故人が亡くなってから6年目の命日に行う法要。
・ 十三回忌:故人が亡くなってから12年目の命日に行う法要。
・ 十七回忌:故人が亡くなってから16年目の命日に行う法要。
・ 二十三回忌:故人が亡くなってから22年目の命日に行う法要。
・ 二十五回忌:故人が亡くなってから24年目の命日に行う法要。
年忌法要の種類と意味
それぞれの法事は、故人の冥福を祈り、その霊を慰めるための儀式であるとともに、故人を偲び、生前の功績を称える場でもあります。
それぞれの法事には、込められた意味合いがあり、その意味を知ることで、法事への理解を深めることができます。
1: 一周忌
一周忌は、故人が亡くなってから初めて迎える命日に行う法要です。
故人を偲び、その霊を慰めるための儀式であり、同時に、故人を失った悲しみを乗り越え、新たな章を始めるための節目でもあります。
葬儀に参列してくれた人たちを招いて、故人との思い出を語り合い、親交を深める場ともなります。
2: 三回忌
三回忌は、故人が亡くなってから2年目の命日に行う法要です。
仏教では、故人は死後49日目に生まれ変わる場所が決まるとされており、三回忌はその生まれ変わりを祝うための法要とされています。
また、三回忌は、故人が亡くなってからしばらく経ち、悲しみが少し落ち着いてきた時期でもあります。
故人を偲び、その霊を慰めるとともに、自分自身の心の整理をつけるための機会でもあります。
3: 七回忌
七回忌は、故人が亡くなってから6年目の命日に行う法要です。
仏教では、七回忌は故人が極楽浄土に生まれ変わるための重要な節目とされています。
故人を偲び、その霊を慰めるとともに、故人が安らかであることを願うための法要です。
4: 十三回忌、十七回忌、二十三回忌
十三回忌、十七回忌、二十三回忌は、それぞれ故人が亡くなってから12年目、16年目、22年目の命日に行う法要です。
これらの法要は、故人が亡くなってから長い年月が経ち、その存在がより一層大きく感じられる時期に行われます。
故人を偲び、その霊を慰めるとともに、生前の功績を称え、感謝の気持ちを伝えるための法要です。
5: 二十五回忌
二十五回忌は、故人が亡くなってから24年目の命日に行う法要です。
仏教では、二十五回忌は故人の魂が完全に成仏する最後の節目とされています。
故人を偲び、その霊を慰めるとともに、故人の魂が安らかであることを願うための法要です。
まとめ
今回は、法事の数え方や種類、意味について解説しました。
法事の数え方は、満年齢ではなく数え年で行うこと、それぞれの法事には込められた意味合いがあることを理解することで、法事への理解を深め、よりスムーズに準備を進めることができるでしょう。
法事は、故人を偲び、その霊を慰める大切な儀式です。
故人を偲び、その霊を慰める気持ちを忘れずに、法事に臨みましょう。