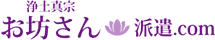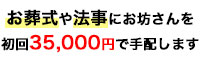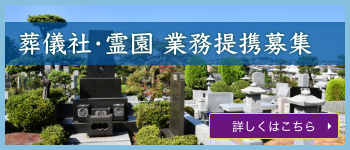大切な方を亡くされ、深い悲しみに包まれている最中、葬儀の準備は多くの負担を伴うでしょう。
特に、戒名に関する手続きは初めてのことばかりで、戸惑う方も多いはずです。
通夜までに必要な準備をスムーズに進めるため、今回は、戒名の準備と通夜当日に向けた具体的な手順を解説します。
戒名の準備と通夜
戒名の意味と種類
戒名は、仏教において故人を称え、仏弟子として極楽浄土に往生することを願って授けられる名前です。
宗派によって「戒名」「法名」「法号」など呼び方が異なります。
構成は、一般的に「院号」「道号」「戒名(法号)」「位号」の4つで、それぞれ故人の人となりや生前の功績などを反映して付けられます。
院号は高位を表し、道号は人格や境涯を表し、戒名(法号)は仏の弟子であることを示し、位号は性別や年齢、社会的地位などを表します。
文字数が多いほど、一般的に位が高いとされていますが、あくまで慣習であり、仏教の教えにおいては平等です。
菩提寺ありの場合の手続き
菩提寺がある場合は、まず菩提寺の住職に連絡を取り、葬儀の日程や戒名の授与について相談しましょう。
菩提寺では、故人の宗派に沿った戒名を授与し、葬儀に関する手続きもサポートしてくれます。
遠方の菩提寺の場合でも、事前に連絡を入れれば、住職が葬儀会場に赴いてくれる場合もあります。
戒名授与は、通夜までに済ませておくのが一般的です。
菩提寺なしの場合の手続き
菩提寺がない場合は、葬儀を依頼する寺院または葬儀社に相談し、戒名授与を依頼します。
この場合、納骨する予定のお寺と宗派が一致しているかを確認することが重要です。
宗派が異なる場合、納骨を拒否される可能性があります。
葬儀社は、宗派に合った寺院を紹介してくれるので、安心です。
また、葬儀を済ませてから、後日納骨先を決めて戒名を授与するという方法もあります。
戒名料の相場と費用
戒名料はお布施として、葬儀後または通夜前に寺院に渡します。
金額は、戒名の位や寺院、地域によって大きく異なり、数万円から数十万円、場合によっては100万円を超えることもあります。
菩提寺がある場合は、これまでの付き合いなどを考慮して金額を決定するのが一般的です。
菩提寺がない場合は、葬儀社などに相場を相談してみるのも良いでしょう。
通夜における戒名の役割
通夜では、故人の霊前で読経が行われます。
戒名は、位牌に記され、故人の名前として読経の中で使用されます。
故人の冥福を祈る上で重要な役割を果たしています。
戒名がない場合は、俗名(生前の名前)に「霊位」などを付けて使用します。
通夜までに必要な手続き
僧侶への連絡と依頼
菩提寺がある場合は菩提寺、ない場合は葬儀社に依頼した寺院に、葬儀の日程と戒名授与の依頼を行います。
僧侶との連絡は、なるべく早めに行うことが大切です。
特に、遠方の寺院の場合は、日程調整に時間がかかる可能性があります。
戒名決定と納経
僧侶は、故人の人となりや生前の様子を考慮して戒名を決定します。
戒名が決まると、納経(戒名を記した経典)が授与されます。
納経は、位牌に貼付したり、仏壇に安置したりします。
通夜に必要な準備
通夜に必要な準備には、会場の設営、供花の用意、参列者への連絡などがあります。
戒名に関する準備としては、位牌の作成や戒名の確認などがあります。
まとめ
通夜までに戒名と葬儀の準備を進めるには、菩提寺の有無を確認し、早めに行動することが大切です。
菩提寺がある場合は菩提寺に、ない場合は葬儀社に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
戒名料の相場も確認し、予算を立てておくことも重要です。
故人の冥福を祈り、遺族の皆様が安心して通夜を迎えられるよう、一つずつ準備を進めていきましょう。
この記事が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。