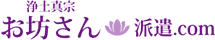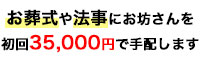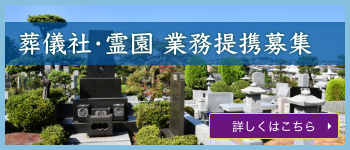老後の不安、それは家族にも降りかかります。
大切な家族の未来のために、今、考えておきたいこと、それは「お墓」のことかもしれません。
先祖代々受け継いできたお墓、あるいは自分自身のお墓について、将来の供養方法を検討されている方も多いのではないでしょうか。
この先、お墓の管理が難しくなった場合、どのような選択肢があるのでしょうか?
永代供養と墓じまい、この2つの方法について、それぞれの特徴や費用、手続きなどを解説し、将来の供養方法を考える上で役立つ情報を提供します。
永代供養とは何か
永代供養の費用
永代供養の費用は、お寺や霊園によって大きく異なります。
合祀の場合は、1霊3万円〜10万円程度と比較的安価ですが、個別のスペースを確保する場合は、20万円〜30万円、場合によっては100万円を超えることもあります。
費用には、永代供養料の他に、開眼供養のお布施(3万円〜5万円程度)、戒名料(必要な場合)、管理料などが含まれる場合があります。
事前に見積もりを取り、費用の内訳をしっかり確認することが大切です。
永代供養の手続き
永代供養の手続きは、まず供養を依頼する寺院や霊園を選びます。
見学や相談を行い、供養方法(合祀、個別、など)や費用、契約内容などを確認します。
契約が成立したら、納骨を行い、永代供養が始まります。
手続きは、比較的簡素な場合が多いです。
永代供養のメリット
永代供養の大きなメリットは、お墓の管理や維持の手間がなくなることです。
後継者がいない場合でも、寺院や霊園が責任を持って供養してくれるため、安心です。
また、遠方に住んでいる場合でも、定期的なお参りがしづらいため、永代供養は負担軽減につながります。
費用面でも、従来のお墓に比べて管理費や修繕費などがかからないため、経済的な負担を減らせる可能性があります。
永代供養のデメリット
永代供養のデメリットとして、供養への参加が制限される場合があります。
合祀の場合、個別の墓参りが難しくなり、供養の感覚が薄れると感じる方もいるかもしれません。
また、一度合祀された遺骨を取り出すことは、基本的にできません。
墓じまいとは何か
墓じまいの費用
墓じまいの費用は、お墓の規模や場所、石材の種類などによって大きく変動します。
一般的な目安としては、30万円〜50万円程度ですが、場合によっては100万円を超えることもあります。
費用には、墓石の解体撤去費用、閉眼供養のお布施(3万円〜10万円程度)、改葬手続き費用、離檀料(寺院墓地の場合)などが含まれます。
依頼前にしっかりと見積もりを取るようにしましょう。
墓じまいの手続き
墓じまいは、まず親族間で話し合い、合意を得ることが大切です。
その後、墓地の管理者へ墓じまいの意向を伝え、手続きを進めます。
改葬許可申請が必要な場合、必要な書類を準備し、役所へ申請します。
改葬許可証が取得できたら、石材店に墓石の撤去を依頼し、遺骨を取り出します。
最後に、遺骨を新しい供養先に移します。
墓じまいのメリット
墓じまいを行うことで、お墓の管理・維持にかかる費用と労力を大幅に削減できます。
遠方にあるお墓の管理に苦労している方や、高齢で管理が困難な方にとって、大きなメリットとなります。
また、後継者がいない場合でも、安心して墓じまいを進めることができます。
墓じまいのデメリット
墓じまいは、手続きが複雑で時間と労力を要します。
行政手続きや業者とのやり取りなど、精神的な負担も大きくなる可能性があります。
また、先祖代々のお墓を撤去することに抵抗感を持つ方もいます。
さらに、墓じまい後の遺骨の供養方法を検討する必要があり、選択肢を検討する必要があります。
遺骨の供養方法
墓じまい後の遺骨の供養方法は、いくつかあります。
永代供養、散骨、手元供養などが代表的な方法です。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるので、ご自身の状況や考え方に合った方法を選択することが大切です。
永代供養は、寺院や霊園が永代にわたって供養してくれる方法です。
散骨は、遺骨を粉末状にして自然に還す方法で、費用を抑えられます。
手元供養は、遺骨の一部を自宅に保管し、身近に供養する方法です。
まとめ
永代供養と墓じまいは、それぞれ目的や手続きが異なる供養方法です。
永代供養は、寺院や霊園に遺骨の管理と供養を委託する方法で、管理の手間や費用を削減できます。
墓じまいは、既存のお墓を撤去し、遺骨を別の場所で供養する方法で、お墓の管理が困難になった場合に有効です。
どちらの方法を選ぶかは、家族構成、経済状況、宗教観など様々な要因を考慮し、慎重に検討する必要があります。
費用面では、いずれも最低50万円程度はかかることを想定しておきましょう。
そして、何よりも大切なのは、家族間の丁寧な話し合いと、それぞれの供養方法に対する理解を深めることです。